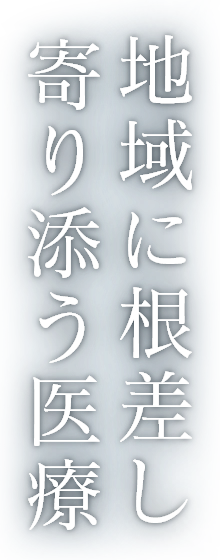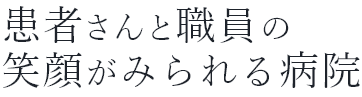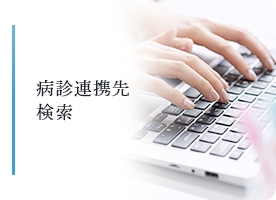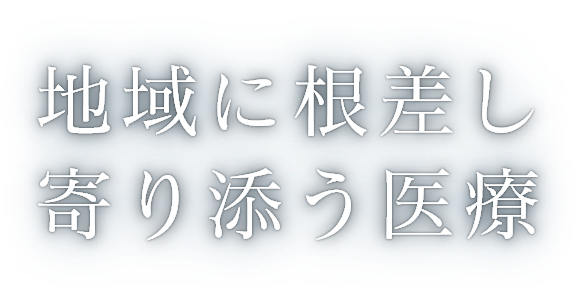
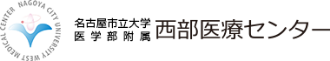
新着情報
すべて
- 2024.04.25
- 休診のお知らせ(消化器外科)
- 2024.04.18
- 分べん介助料改定のお知らせ
- 2024.04.08
- 名古屋市立大学 管理栄養士(令和6年度途中採用)【名古屋市立大学固有職員】の募集
- 2024.04.01
- 名古屋市立大学 臨床検査技師(令和7年4月採用)【名古屋市立大学固有職員】の募集
- 2024.03.25
- 医学部学生の臨床実習について
お知らせ
- 2024.04.25
- 休診のお知らせ(消化器外科)
- 2024.04.18
- 分べん介助料改定のお知らせ
- 2024.03.25
- 医学部学生の臨床実習について
- 2024.03.18
- 乳腺・内分泌外科 セカンドオピニオン専用外来を開設します
- 2024.03.01
- 相談窓口お休みのお知らせ(がん相談支援センター)
採用情報
- 2024.04.08
- 名古屋市立大学 管理栄養士(令和6年度途中採用)【名古屋市立大学固有職員】の募集
- 2024.04.01
- 名古屋市立大学 臨床検査技師(令和7年4月採用)【名古屋市立大学固有職員】の募集
- 2024.03.21
- 名古屋市立大学 臨床検査技師(令和6年度途中採用)【名古屋市立大学固有職員】の募集
- 2024.03.21
- 名古屋市立大学 薬剤師(令和7年4月1日採用)【名古屋市立大学固有職員】の募集
- 2024.03.18
- 名古屋市立大学 臨床工学技師(令和7年4月1日採用)【名古屋市立大学固有職員】の募集
イベント・講座
- 2024.01.05
- 「がん患者サロン」開催のお知らせ